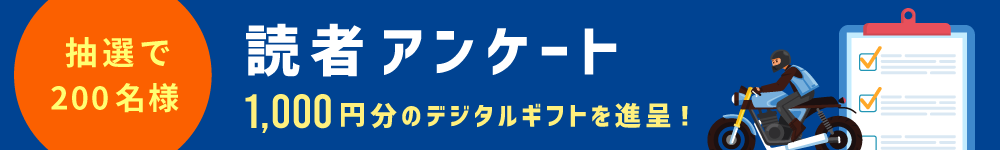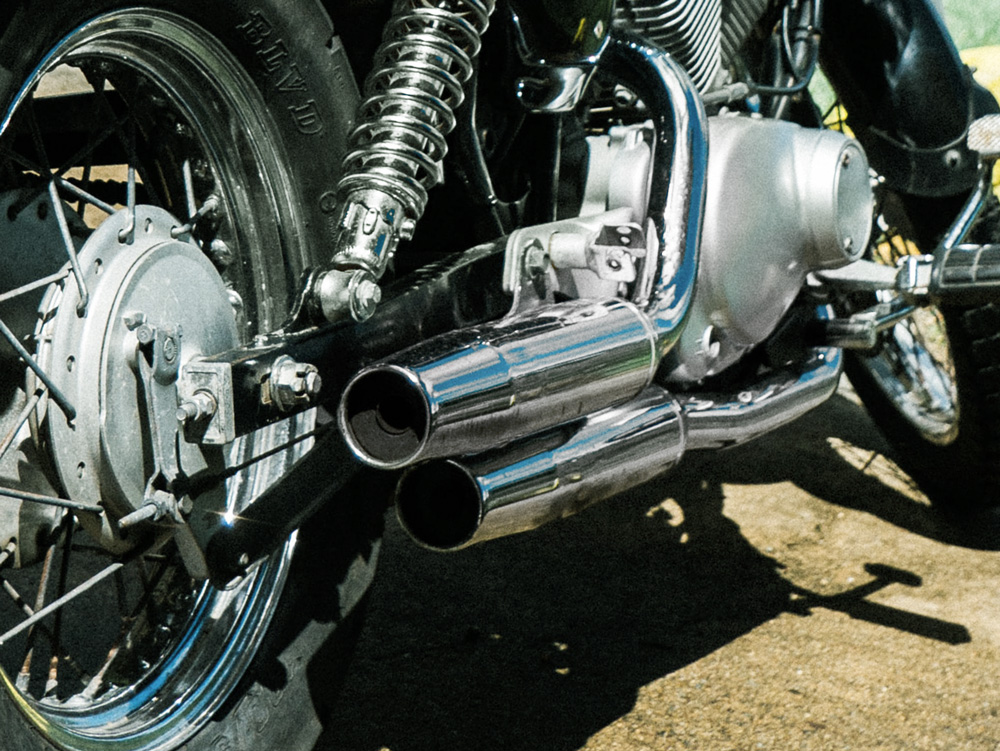安全に原付バイク通学するための支援を行う神奈川県の取り組みを追う
目次 - INDEX
都市以外での人口減少により地域のバスの輸送人員が減っており、地方の公共交通網の脆弱性が浮き彫りになってきています。今年9月に宮崎で開催された「第12回 BIKE LOVE FORUM in 南国みやざき」(以下、BLF) でのパネルディスカッション「電動二輪車利活用による社会課題(脆弱な二次交通)解決」でも議論されていたのは記憶に新しいところです。
今回お話を伺った神奈川県立津久井高等学校(以下、津久井高校)もその影響を受けた学校の一つで、通学に利用されていた地域バスの減便により、生徒の通学が困難な状況になりました。
その現状を打破する方法として、津久井高校は原付バイクでの通学を認可しました。現在、神奈川県二輪車普及安全協会(以下、神奈川二普協)と神奈川県警察(以下、神奈川県警)による安全運転のための支援活動を受けながら、安全にバイク通学できる環境を整えています。そのような取り組みと現状を津久井高校に取材しました。
バイク通学の認可に至った背景

津久井高校は、神奈川県相模原市の北部に位置する津久井湖のすぐ近くにある普通科の高校です。1902年に蚕業専門学校として始まった古い歴史を持つこの高校は、神奈川県から山梨県へと至る街道途中の山間部に位置することから、通学が容易ではなく以前より最重要課題にあげられていました。
最寄りのJR横浜線・橋本駅から津久井高校の近くまで運行している路線バスだと約45分かかり、バス代も1日往復で1,000円を超えます。通学用の定期券でも10万円を超えてしまい、経済的な負担は少なくありません。山梨県側から通学している生徒の場合は通学に適したバスが通っておらず、毎日親が自家用車で送迎することもありました。スクールバスを導入するにはかなりの予算が必要になり、津久井高校にはそこまでの余裕はありませんでした。

こうした通学の負担を少しでも軽減しようと出された案が、「原付バイクでの通学」でした。ここで学校として懸念されるのが「安全にバイク通学ができるのか」という点ですが、バイク通学する生徒は講習会の受講を義務とし、神奈川県警と神奈川二普協と連携し安全運転講習会を実施することとしました。実技講習(年1回)と座学講習(年3回)を毎年行い、2025年1月現在まで大きな交通事故は一件も発生していないそうです。
神奈川二普協と神奈川県警による支援活動

津久井高校が年に一度行っている実技講習が2024年12月、最寄りのライディングスクールにて催されました。指導したのは、神奈川県警女性白バイ隊の「ホワイトエンジェルス」で、実際の公道走行時に必要なライディングスキルと、安全運転への意識向上のためのレクチャーが行われました。

今回の津久井高校の安全運転講習会は、「急制動」「スラローム」「一本橋走行」「低速方向転換」という4つが組み込まれた、大きな排気量のバイクの実技講習と変わらないレベルのカリキュラムでした。それを現役の白バイ隊員が指導するのですから、一般的なライディングスクールと変わらない内容といえます。
ホンダ「スーパーカブ50」で通勤しているという熊坂校長を含んだ11名が参加した講習会は、実際に車両に乗る前に身体の柔軟体操と、両手を不規則に動かす頭の柔軟体操から取り組みます。脳を活性化させて判断力や柔軟性を刺激したところで、次にバイクの点検を行います。ブレーキやタイヤ、灯火類、燃料など、乗車前に必ず実施すべきポイントを点検し、乗車装備を着用していよいよコースインです。
各セクションに「ホワイトエンジェルス」が立ち、生徒にアドバイスを送ります。それはライディングの方法はもとより、公道走行を想定して求められるライダーのマインドや、他の車両や歩行者への対応方法など、日々のバイク通学にそのまま活かせる具体的な内容でした。

小型二輪、普通二輪、大型二輪の免許を取得するために教習所に通えば、スラロームや一本橋走行、急制動は当然のようにカリキュラムに組み込まれています。これらのカリキュラムは公道を走る原付ユーザーも体得しておくと良い内容です。スキルアップはライディングに余裕を生み、視野を広げられて周囲の状況を今まで以上に把握できるようになります。それがひいては危険な状況を予測することにつながり、安全にバイク通学できるようになるのです。バイク通学が始まったこの5年間で一件も大きな事故が発生していないのは、この安全運転講習会の成果です。
バイク通学している生徒の印象は

高校1年生の冬からバイク通学を始めた薄葉さんは、今回が3回目の講習会参加です。
「通学費用はすべて自分で負担しているので、バイクも自分で買って、バイク通学を選びました。悪天候でもバイクで通っているので、他のクルマや歩行者への配慮を考えて安全運転を心がけています。
講習会はいつも楽しいです。卒業したらクルマの免許を取得する予定ですが、バイクには乗り続けたいと思っています。原付二種のバイクに興味がありますね」
学校側の視点

熊坂 和也 氏
ご自身もバイク乗りという熊坂校長は、率先して愛車のホンダ・スーパーカブ50で通勤されています。「バイク通学」を認可されたご本人でもあり、学校側の視点を以下のように語りました。
「津久井高校は山間部にあることから、以前から『生徒の通学費用がかかりすぎる』という父兄からの意見が届いていました。そこで『バイク通学』というアイディアが出たのですが、当初はかなり反対されるだろうと思っていたんです。
ところが、学校の職員からは賛成意見も出てきました。というのも、職員のほとんどが自家用車で通勤しており、学校の立地を考えると(バイク通学という案も)検討すべきだろうとのことでした。ポジティブな反応から始まった『バイク通学』案は、『取り組むなら安全面の指導をしっかりしよう』という内容で進み、『バイク通学』導入となりました」

「バイク通学」導入に際して、すでにバイク通学を認めている学校にも視察に赴いたという熊坂校長。やはり「安全性の確保」がもっとも重要で、神奈川県警にも相談して現在のスタイルが生まれました。
津久井高校の周辺住民による理解の大きさも、導入に向けての後押しとなったと熊坂校長。「学校が認めた制度として、堂々とバイク通学できるようになった方が安全運転への意識も高まるはず」という声が出てきて、校舎の正面入り口前に駐輪場を設けるなど学校の前向きな姿勢が形になりました。

通勤にバイクを使うこともある熊坂校長は、バイク通学実施から毎年この安全運転講習会に参加しています。
「導入したからには、自分自身も安全運転を学んで、そのうえで生徒を指導していこうと思うんです。バイクで公道を走るという点では、教師も生徒も同じ立場ですから」
楽しみながら安全運転を学ぶ熊坂校長の姿が、津久井高校が導入したバイク通学が明るいものであることを表しているようでした。
社会課題に対するひとつの答えがここに

宮崎で開催したBLFのパネルディスカッション「電動二輪車利活用による社会課題(脆弱な二次交通)解決」で課題とされた「地方の交通インフラが脆弱になりつつある」という実態がそのまま津久井高校で起こっていました。その解決策の一つとしていち早く「バイク通学」が導入され、高校生に安全運転指導を行ったうえで運用するという、バイクが社会課題の解決策となるひとつの成功事例を見ることができました。
1970年代後半から広まった「三ない運動」(バイクの免許を取らない・バイクに乗らない・バイクを買わない)が起こってから、高校生がバイクで通学するのはタブーとされてきました。その三ない運動も耳にすることがなくなり、正しく安全に使えばバイクは有用なパーソナルモビリティとなることがようやく理解されつつあります。
環境によって解決策が異なる地方の交通インフラという問題に対して、津久井高校のバイク通学と安全運転への取り組みはひとつの答えとなっています。同じような課題を抱えている学校関係者の方は、津久井高校の取り組みを事例として、地元の警察や二普協支部にお問い合わください。